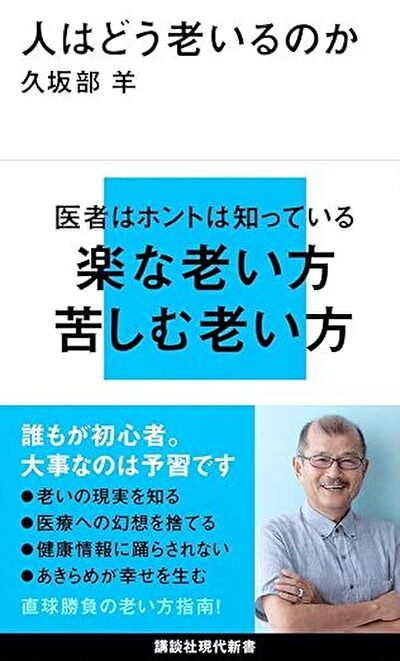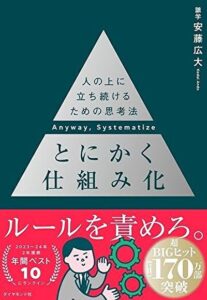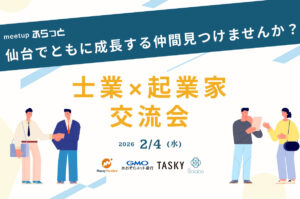こんにちは!タスキーグループ税務支援チームの上野です。
先日、大学時代の友人とアンパンマンミュージアムへ行ってきました。2児の父である友人が、事前に私のことをお子さんに話してくれていたようで、会うなり「このおじさん分かる?」と話しかけられました。その時、「おじさんか…確かに“お兄さん”ではないな…」と、年齢を重ねていることを実感しました。
それ以外にも、椅子から立ち上がる際に膝の痛みを感じたり、10年間以上変わらなかった体重が少し増えたりと、身体の変化を感じることが増え、「老い」が自分ごととして捉えられるようになりました。
漠然と祖父母の姿やその変化を見ていましたが、一般的に人はどう老いていくのかを知る機会はこれまでありませんでした。そんな中で手に取ったのが、久坂部羊さんの著書『人はどう老いるのか』です。
本書を読んで最も印象的だったのは、「老いを自覚することの難しさ」です。私たちは自分の体調の変化や不調について、「一時的な不調だろう」「医者に診てもらえば治る」「こんな健康法が効くらしい」など、つい楽観的に考えてしまいます。(私自身も増えた体重は数か月後に戻ると思っています笑)
しかし、著者は老人デイケアで勤務された経験から、私たちの考えを見直すきっかけを語ってくれています。例えば、以下のようなものです。
・医者がすべての病気を治せるわけではない
・認知症の有効な予防法は、残念ながらまだ明らかになっていない
・医学的根拠のない商品も市場に多く存在する
だれもが避けたいと思ってしまう「老い」を自覚し、受け入れるためには、身体の変化を自覚するための心の準備期間が必要だと感じました。心身の成長に思春期という準備期間があるように、私たち大人にも「老い」と向き合うための「第二思春期」と呼べるような時間が必要なのでしょう。
「自分はまだ大丈夫」と楽観的になりすぎず、かといって悲観的にもなりすぎず、自然体で「老い」を受け入れられるようになりたいと思いました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
タスキーグループ 税務支援チーム 上野 鎮