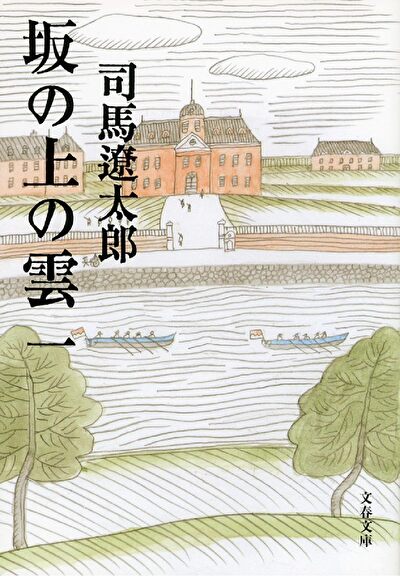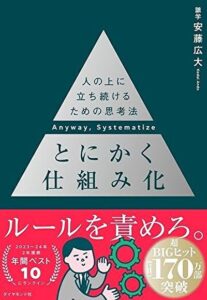こんにちは!タスキーグループ/税務チームの菊池です。
今回紹介する「坂の上の雲」は、伊予松山出身の3人の青年――日露戦争の勝利に貢献した秋山好古・秋山真之兄弟、そして俳人・正岡子規――を主人公にした長編小説です。
私自身、この本が大好きで何度も読み返してきました。今月初めに松山へ出張し、「坂の上の雲ミュージアム」を訪れたことをきっかけに、あらためて紹介したいと思います。数えきれないほどの学びがありますが、今回は特に心に残っている2点を挙げます。
① 明治の人々の人生に対する姿勢
登場人物たちは皆、まっすぐに自分の人生を生きています。その姿に、読むたび胸を打たれます。
司馬遼太郎はあとがきの中で、当時の日本についてこう記しています
「政府も小世帯であり、ここに登場する陸海軍もうそのように小さい。その町工場のように小さい国家のなかで、(中略)スタッフたちは世帯が小さいがために思うぞんぶんにはたらき、そのチームをつよくするというただひとつの目的にむかってすすみ、その目的をうたがうことすら知らなかった。この時代のあかるさは、こういう楽天主義からきているのであろう。」
当時の人々のひたむきな努力が今の私たちの暮らしにつながっていると思うと、自然と感謝の気持ちが湧いてきます。
また、大変僭越ながら、タスキーがValueに掲げる「目的志向と目的思考」にも通ずるところがあると感じています。
② セレンディピティを掴む力
セレンディピティとは、偶然の出会いや出来事をきっかけに成果を得る力のことです。
歴史上の偉人はこの力に優れていたと感じます。
本作の主人公、秋山真之は、海軍の若手将校時代、当時二流国とされていたアメリカへ留学することになりました。留学枠が限られ、最年少の彼にはイギリス等当時の一流国行きの機会が回らなかったからです。
しかしこの偶然の選択が大きな幸運をもたらしました。アメリカに行かなければ得られなかった貴重な経験が、のちの海軍参謀への抜擢、そして日本海海戦の戦術立案につながったのです。
とはいえ、真之は仮にイギリスに行っていたとしても、きっと別の形でチャンスを掴んでいたのだろうとも思います。彼は米国留学中、著名な戦術家に師事し、大学の図書館に通いつめて日夜勉強を重ねていました。そうした不断の努力があったからこそ、偶然訪れた機会を成果につなげることができたのだと思います。
セレンディピティは確かに追い風になりますが、それ自体が必須条件ではありません。結局は「与えられた環境をどう活かすか」にかかっているのだと感じます。
これは現代を生きる私たちにとっても変わらない普遍的な姿勢ではないでしょうか。
全8巻ととても長い本作ですが、読書の秋にぜひ読んでみてください。
最後までお付き合いいただきありがとうございました!
タスキーグループ/税務チーム 菊池 友博
参照:坂の上の雲/司馬 遼太郎