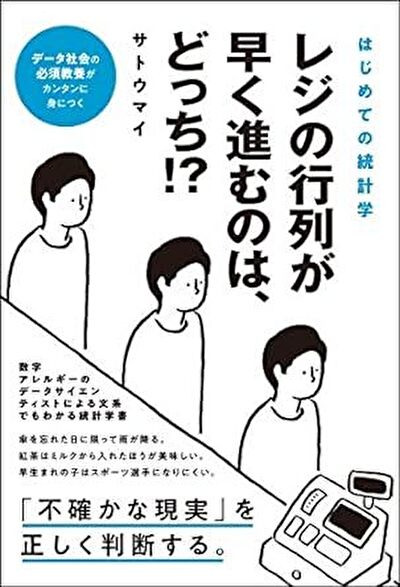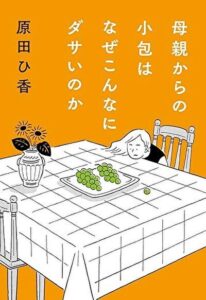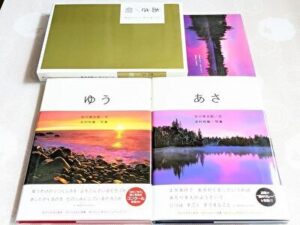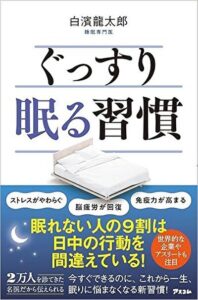こんにちは!タスキーグループ労務支援チームの木下知奈美です。
涼やかな空気に包まれ、心も少し落ち着きを取り戻す秋の訪れを迎えました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回ご紹介する本は、『はじめての統計学 レジの行列が早く進むのはどっち!?「不確かな現実」を正しく判断する術』です。
この本を手に取ったのは、タイトルのとおり、会計等の際に私の並ぶ列はだいたい進みが遅く自分より後に並んだ隣の列の人の方が先に会計が終わっているなんていう事が日常的にあり、早く進むレジの列が統計学で分かるの?という純粋な興味からこの本を選びました。
【レジの行列が早く進むのはどっち!?】
突然ですが、一生のうちにレジに並んでいる時間はどれくらいあると思いますか?
寿命を80年として、20歳から毎日レジに並んで買い物をすると仮定すると、
(80-20)年×365日=2万1900回
この半分を「前の人の会計を並んで待っている状態」で、平均3分待つとします。
21,900回×1/2×3分=32,850分=547.5時間=約23日間
人生の中で約23日間も「ただ待つだけ」という時間があるということです。
この何もしないただ待つという時間をいかに短縮させるべく、レジ戦争に勝ち抜く方法が
この本では紹介されています。
~以下の順番で並ぶ列を見極める~
① 2人体制のレジに並ぶ
② レジが開く可能性がある
③ 手際がいいレジ係がいる
④ かごの中身が少ない
無意識に④の「かごの中身が少ない」人の後ろに並ぶという選択をしている人が多いのではないでしょうか?ただ、このかごの中身の量は極端な量の差でない限り現実的にそこまで見分ることが難しく効果はあまり期待できないと著者は言います。
①の「2人体制のレジに並ぶ」だと一人の作業を2人でやる方が単純に処理能力が2倍になるので早いと思いますが、統計学を用いて計算すると待ち時間は2倍どころか5倍以上も短縮される計算になります。その為2人体制のレジがある場合、待ち人数が1~2人多くてもその列に並んだ方が会計が早く終わるそうです。
本書ではより細かく統計学の観点から計算式を用いてなぜこの順番になるのかという事が説明されています。
他にも面白いトピックスがあったのでご紹介します。
【じゃんけんには必勝法がある!?】
2009年に日本経済新聞に掲載された、「じゃんけんに関する研修結果」によると、
グーを出す確率35%、チョキを出す確率33.3%、パーを出す確率31.7%となり、グーを出す人が一番多いという結果が出たそうです。
つまり「パーを出すのが最も勝ちやすい選択」ということです。
このように統計学を用いればじゃんけんの勝率を上げる事もできるのです。
他にも「お金が貯まらない本当の理由」「ミルクティーはミルクから入れた方が美味しいのか」等生活の身近なテーマを通じて、統計学というものが分かりやすく説明されており、日常生活に役立つ判断力を養うことができます。
人は一日2万回以上の選択をしていると言われます。日常的な小さな選択(朝何を食べるか、どの道を通るかなど)から、大きな決断(仕事の選択や人間関係の決定など)まで様々です。
皆さんもその選択に統計学という手段を用いてみてはいかがでしょうか?
もしかしたら時間を少し短縮できたり、小さなチャンスをつかむ事ができるかもしれません。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。