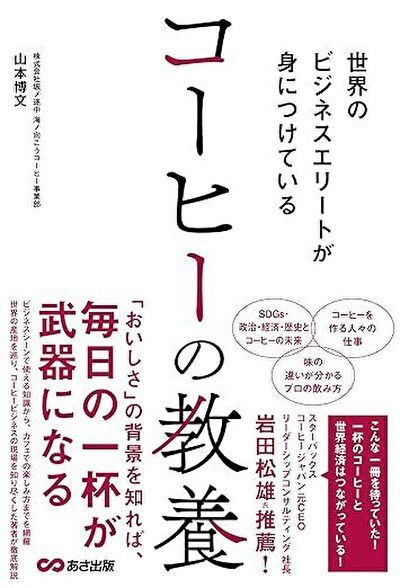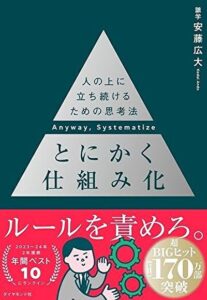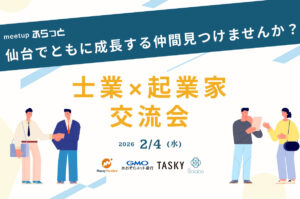こんにちは!タスキーグループ労務支援チームの木下です。
寒さが日に日に増してきましたね。
朝、ホットコーヒーの香りに包まれると、それだけで少し幸せな気持ちになります。
毎朝飲むその一杯が届くまで、どんな世界が広がっているのだろうと思っていたとき、出会ったコーヒーにまつわる一冊をご紹介します!
『コーヒーの教養』 / 山本博文 著
本書は、コーヒーの味や楽しみ方だけでなく、歴史や文化、産地ごとの特徴、さらには経済や社会の仕組みまで幅広く学べる一冊です。
コーヒーは17世紀半ば頃、ヨーロッパに広まりました。
カフェインの覚醒作用が労働者にとって必要なエネルギー源となり、喫茶店の原型である「コーヒーハウス」は新しいビジネスが生まれる場所として、多くの実業家が集う場所となりました。
また、コーヒーにも野菜のように旬があるのをご存知ですか?
冬はブラジル、春はエチオピアやインドネシア、夏はコスタリカなど、産地ごとに「飲み頃」の時期があります。
さらに、精選処理や品種、生産国の気候風土によって味わいが大きく変わるのも特徴です。
こうした味の違いを楽しむには、まず飲み比べて自分の味覚の解像度を上げるとよい、と筆者は言います。
最初は「苦みか酸味か」「すっきり軽めか、コクが深いか」を比べてみましょう。
大まかな好みが分かったら、次は産地別に飲み比べてみてください。
例えば深煎りでも、ケニア産は「苦みとほのかな甘み」、インドネシア産は「苦みとフルーツのような甘み」が感じられます。
最後に、美味しく淹れるポイントを少しだけご紹介します。
・豆とお湯の量に注意
一般的にコーヒー一杯(約120cc)には10gの豆が目安です。
豆を増やすと濃厚な味わいになり、酸味や苦みが強まります。減らすとマイルドに。
・豆の挽き目を調整
粒度が細かいほど成分が抽出されやすく、味わいが濃くなります。渋みも出やすくなります。
・お湯の温度を意識
高温のお湯ほど豆の成分が出やすく、酸味やフレーバーが際立ちます。
奥が深いコーヒーの世界。
まずはこの一冊から始めてみてはいかがでしょうか?
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!
タスキーグループ/労務支援チーム 木下 知奈美