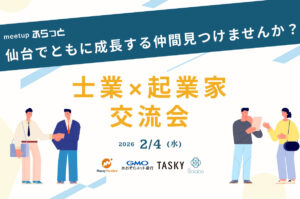本日もご覧いただきありがとうございます。
タスキー株式会社、学生インターンの髙橋です!
今回紹介させていただくのは、こちらの一冊です。
「図解 無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい」
本書は、仕組みを大切にする働き方が紹介された1冊です。
業績が大きく落ち込み、無印良品は終わりなんじゃないか、と囁かれていた時期。
社長に就任した著者は、「仕組みづくり」を始めました。
具体的に本書で多く事例があがっているのは、マニュアルづくりです。
現在無印良品には、各店舗運営と本部業務について2,000ページ以上のマニュアルがあるそうです。
無印良品は、なぜマニュアルづくりを重視したのでしょうか。
著者は、業務の標準化を通して「社会の変化に対応できる機動力のある組織に進化させたい」という思いを持っていたそうです。
業務の標準化には、これらのメリットがあります。
①現場で働く人の知恵や経験を共有できる
②業務を誰が行っても一定の質を保てる
③上司固有のノウハウで部下を育てる文化から決別できる
④組織の理念をくり返し伝えられる
⑤マニュアルを更新する段階で、普段行う作業の課題、あるべき姿を考えられる
仕組みづくりは、組織の体質を変え、働く人の意識を変える重要な役割を持つと筆者は説きます。
では、無印良品はマニュアルづくりの際、どのような点を重視したのでしょうか。
本書にあげられている事項の中で、特に印象に残っている点を5つお伝えします。
①マニュアルはできた瞬間から陳腐化する。定期的に改善し、業務の最高到達点にする
②1人のトップがつくるのではなく、社員全員で1つ1つの業務を丁寧に検討しながらつくることが重要
③読む人によって判断軸がぶれる表現はせず、新入社員でも理解できるものを目指す
④更新の際は、現場からの改善提案を大切にする。ただ、全てを受け入れるのではなく、マニュアルの管轄者が、
他業務との重複や、全体最適かをチェックする
⑤どんな作業の説明も、なぜ?を伝える。また、ミスやトラブルは今後の注意点として蓄積する
また、本書では、無印良品のマニュアルの実例も一部紹介されています。
印象的だったのは、一見センスが問われるような仕事や、無印良品”らしさ”も、細やかに言葉にし、誰もが業務に活用できる状態になっていることです。
例えば、マネキンのコーディネートの考え方、商品タイトルのつけ方、新規出店の意思決定方法など、難易度の高い業務にもマニュアルが作成されています。
マニュアルというと、一見無機質で、「これに従えばいいや」と働く人の思考を止めてしまうもののように思えますが、
無印良品の洗練された世界観、どんどん新たな商品が生まれる発想力の源泉は、業務の標準化により生まれる機動力なのだと、実感させられました。
今回は仕組みづくりの本を紹介させていただきました。
私はタスキーの他、いくつかの学生組織で活動をしています。
学生組織は(少なくとも私の組織では)、「何かを残すこと」が苦手です。
人材の入れ替わりが激しく、リーダーの役割を担う代も毎年変わる点から、
「この1年をどう送るか」が思考の中心となり、
「組織の未来をよりよくする」ための行動が、どうしても後回しになってしまうのです。
そんな中本書に出会い、また、タスキーでのお仕事を始め、学習する組織の重要性を学びました。
1年ほど前に読んだ本なのですが、卒業直前の今もう1度読み直し、気が引き締まる思いです。
未来へ思いを紡ぐこと。
学生組織での活動はもちろん、タスキーでのお仕事も、できることから一歩ずつ歩みを進めていこうと思います。
本日もご覧いただきありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします!
タスキー株式会社 髙橋俊英